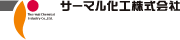よくある質問
熱処理・水素還元技術ナビのよくある質問
こちらのページでは、熱処理・水素還元技術ナビへ寄せられた
ご質問のご回答を紹介しております。
下記以外にも不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。
水素還元
-
ケイ素鋼粉末の水素還元処理を行いたい。
-
クロム含有の粉末を還元したいのですが。
-
レアアースの中で水素還元できるものは何ですか?
-
レアアースの水素還元温度はどれくらいですか?
-
レアアースの水素還元は可能ですか?
-
銅合金の溶解温度近くで水素還元可能ですか?
-
銅合金の水素還元は可能ですか?
-
銅粉末水素還元温度はわかりますか?
-
銅粉末の水素還元は出来ますか?
-
水素還元の仕組みについて教えてください。
-
水素還元は高温に対応可能ですか。
-
水素還元で対応可能な熱処理温度を教えて下さい。
-
水素焼鈍の条件について教えて下さい。
-
水素雰囲気熱処理は何度から対応可能でしょうか。
-
水素雰囲気焼鈍について教えてください。
-
ウェット水素とは何ですか?
-
水素還元温度について教えてください。
-
還元性について教えてください。
-
水素中の水分量について教えてください。
-
水素焼鈍炉は、ニッケルの少ない鉄に対して使用しても大丈夫でしょうか?
-
水素は金属より酸化しやすいのでしょうか。
-
水素ガスが結露することはありますか。
-
水素還元の反応式の一例を教えてください。
-
水素熱処理1バッチの価格について教えてください。
-
水素還元を行った場合、酸素と置き換わった水素はその後どうなるんでしょうか?
-
水素還元の温度について教えてください。
-
水素雰囲気熱処理に付いてわかりやすく教えてください。
-
熱処理に必要な水素の量はどれくらいですか。
-
水素中熱処理の場合、水素の濃度はとは何ですか?
-
水素雰囲気熱処理の後に同じタンクで窒素雰囲気熱処理をすることは可能ですか?
-
空気中の水素だけで還元することはできますか。 また、どのくらいの水素で銅1gを還元できますか。
-
水素還元ガスの利点について教えてください。
-
水素還元力とは何ですか。
-
水素ガスを使った熱処理で長時間処理には対応しておりますか。
-
水素雰囲気で何℃から何℃までの温度の熱処理に対応可能ですか。
-
水素還元とはどのような熱処理ですか?
熱処理の基礎
-
ベリリウム銅を素材のまま処理したい。
-
コバールの焼鈍を行いたい。
-
磁気焼鈍の価格について教えてください。
-
応力除去焼鈍で、歪取りができるとの事ですが、どういったメカニズムですか?
-
光輝焼鈍炉の雰囲気ガスについて教えてください。
-
SUS630について教えてください。
-
窒素雰囲気は不活性ガスとしての役割があるのでしょうか。
-
SUS304の固溶化処理は出来ますか?
-
焼鈍を行うときの注意点を教えてください。
-
水素雰囲気下での脱炭の仕組みについて教えてください。
-
時効硬化処理について教えて下さい。
-
ステンレスの熱処理目的について教えてください。
-
水素還元の反応エンタルピーはどうなっていますか?
-
ベイナイトについて教えてください。
-
タフピッチ銅の熱処理について教えてください。
-
純鉄は焼き入れすれば硬くなりますか。
-
SPCC材は磁気焼鈍を考えております。 情報を集める中でSPCC材は焼鈍の効果が薄いとありますが、 実際効果は出るのでしょうか。
-
C3602材(カシメ材)の焼鈍は対応可能でしょうか。
-
FeNiめっき皮膜の磁気焼鈍を検討しています。100*100mmのサンプルを数枚だけ処理とかにも対応しているでしょうか。
-
応力除去焼鈍でも鉄の磁気特性は改善しますか?
-
SUS304でも低温脆性が起こるのでしょうか?また、低温脆性がおきた場合の素材が常温になった場合、機械的性質が変化しているのでしょうか?
-
SUYとは何ですか。
-
固溶化熱処理は応力除去の目的も含んでいますか。
-
分散強化について教えてください。
-
磁気焼鈍は図面上でどのように表記すればよいのでしょうか。
-
水素ガスと空気を置き換える「置換」方法とは具体的はどの様な方法でしょうか?
-
真空磁気焼鈍と無酸化磁気焼鈍の違いについて教えてください。
-
酸化について教えてください。
-
水素還元反応がメッキに与える影響はありますでしょうか。
-
熱処理の工程変更の難易度について教えてください。
-
HVの意味について教えてください。
-
パーカー処理可能でしょうか?
-
純鉄を焼き入れするとどうなりますか。
-
SUS430の焼鈍は磁気焼鈍だけでしょうか?普通の焼鈍はしますか?またその条件は?
-
水素焼鈍でなぜ鋼は水素脆化しないのでしょうか。教えてください。
-
焼きなましはどこに使われているのか教えてください。
-
光輝焼鈍について教えてください。
-
高周波焼き入れについて教えてください。
-
銅C1100P-1/4Hの熱処理について教えてください。
-
雰囲気について教えてください。
-
保持力を小さくするのかなぜでしょうか。
-
焼入れの起源は何ですか?
-
真空還元について教えてください。
-
加工前に試料である純鉄の熱処理は必要でしょうか。
-
耐熱温度について教えてください。
-
窒素雰囲気熱処理は何に使われるか教えてください。
-
サーマルやサーマル化とはどのような意味でしょうか。
-
インコネル時効処理前の硬さについて教えてください。
-
アニール処理の特長について教えてください。
-
純鉄の焼入れにより組織がどうなるか教えてください。
-
純鉄の焼入れは可能ですか?
-
パーメンジュールについて教えてください。
-
純銅の熱処理についてについて教えてください。
-
浸炭焼き入れの始まりは何ですか。
-
VACOFLUX50の磁気焼鈍に対応できますでしょうか。
-
磁気焼鈍とはどんな処理か教えてください。
-
金属とは何ですか。
-
AN-M-Vについて教えてください。
-
炭素鋼(S-C材)の加工後の磁気焼鈍処理で材料の比透磁率が大きく変わるのでしょうか
-
アルゴン雰囲気について教えてください。
-
連続炉について教えてください。
-
熱処理はどんな時に用いられますか?
-
A0変態点について教えてください。
-
L/T(エルT)について教えてください。
-
ステンレスを熱処理して得られる特性について教えてください。
-
還元は試料から酸素を奪うことを差すと思いますが、逆に酸化は試料から何を奪うのでしょうか。
-
ポット炉とは何ですか?
-
析出硬化についてについて教えてください。
-
析出硬化処理について簡単に教えてください。
-
炉の仕組みについて教えてください。
-
熱するとなぜ磁性が生まれるのか教えてください。
-
水素は循環しますか
-
中性雰囲気について教えてください。
-
SUSなどに水素還元をして表面積が増加するようなことはありませんか。
-
水素を使用する理由について教えてください。
-
一般的なガスの露点について教えてください。
-
酸素分圧が低い方が還元されますか。
-
磁気焼鈍とはについて教えてください。
-
応力除去焼鈍について教えてください。
-
磁気焼鈍一回にかかる電力量を教えてください。
-
磁気焼鈍後に磁化してしまう原因はなんですか?
-
真空について教えてください。
-
水素で脱炭は可能でしょうか。
-
大気中での熱処理で表面が酸化することはありますか。
-
焼入れできるステンレスについて教えてください。
-
脱ガスについて教えてください。
-
異種金属の溶接後の熱処理温度について教えてください。
-
露点とはなんですか?
-
磁気熱処理(水素熱処理)ができる形状について教えてください。
-
パーマロイの熱処理方法について教えてください。
-
結晶成長について教えてください。
-
SWCHの磁性について教えてください。
-
磁気焼鈍と普通の焼鈍の違いを教えてください。
-
鉄はいつ生まれましたか。
-
500度一時間の耐熱試験をしたいのです。
-
窒素を使うことで金属の酸化が防げるプロセスを教えてほしいです。
-
SUS304の鍛造・切削品において、応力除去焼鈍処理は、 通常、鍛造と切削加工の間に行われますでしょうか。それとも切削工程の後の最後の工程で行われますでしょうか。
-
INCONEL718の応力除去について教えてください。
-
脱炭について教えてください。
-
窒素の露点について教えてください。
-
中間焼鈍について教えてください。
-
特殊ガスを使った熱処理例はありますか?
-
一番最初に使われた金属について教えてください。
-
A5056をアニール処理する場合に水素雰囲気は可能でしょうか。
-
マルテンサイトについて教えてください。
-
スケールによる脱炭について教えてください。
-
鉄について教えてください。
-
脱炭のメリットについて教えてください。
-
黄銅の応力除去の条件について教えてください。
-
SUS316の応力除去方法を教えてください。
-
磁化について教えてください。
-
インコネルの熱処理について教えてください。
-
浸漬について教えてください。
-
磁気焼鈍と窒化処理はそもそも異なる処理方法ですか。
-
焼鈍の目的について教えてください。
-
1番最初の金属はなんですか。
-
析出硬化処理について教えてください。
-
鉄が初めて開発された場所はどこですか。
-
試料の純度の違いにより、析出硬化の起こりやすさは決まっていますか。
-
析出硬化処理は完成品に行うのでしょうか。
-
SUS304を熱処理するとどうなりますか?
-
浸炭について教えてください。
-
インコネル718の熱処理はできますか?
-
アルゴン雰囲気の熱処理について教えてください。
-
人類の歴史の中で二番目に早く普及した金属はなんですか?
-
磁気焼鈍の意味について教えてください。
-
窒素雰囲気下による還元反応についてについて教えてください。
-
インコネル718析出硬化処理後のHRCはどのくらいについて教えてください。
-
swch-6rの焼鈍について教えてください。
-
磁気焼鈍と応力緩和焼鈍の違いについて教えてください。
-
SUS304は熱処理必須ですか?
-
水素の排ガスはどう処理しているか教えてください。
-
還元雰囲気について教えてください。
-
パーマロイを磁気焼鈍するかしないかでどれくらい透磁率が変わりますか?
-
雰囲気とはどういう意味ですか?
-
SPCEの磁気焼鈍の方法について教えてください。
-
インコネル601時効硬化処理について教えてください。
-
SUS304の処理温度は何度ですか?
-
ステンレス鋼の熱処理の方法について教えてください。
-
焼鈍で脱炭しますか。
-
磁気焼鈍後の検査項目について教えてください。
-
HA・Hについて教えてください。
-
チタンの熱処理はできますか。
-
保磁力の数値化はされるものでしょうか、教えてください。
-
パーマロイの成分を教えてください。
-
磁気焼鈍について教えてください。
-
鋭敏化について教えてください。
-
磁気を強くする方法を教えてください。
-
ステンレスの焼鈍は対応可能でしょうか。
-
析出硬化処理は行われていますか?
-
炉内加熱で使われる耐火物について教えてください。
-
磁性ステンレスの熱処理で特性管理の難しい点を教えてください。
-
Fe-c系平衡状態図について教えてください。
-
大気焼鈍で光沢が出る可能性はありますか。
-
水素雰囲気で加熱したらどうなりますか。
-
酸化スケールの密着性について教えてください。
-
液体窒素ガスの水分含有量を教えてについて教えてください。
-
脱炭のメカニズムを教えてについて教えてください。
-
黄銅の180℃での焼鈍は効果がありますか?
-
IA処理とは、また焼準について教えてください。
-
Fe-Cr-Co合金の磁場中熱処理はされていますでしょうか。
-
焼鈍すると硬さはどうなるか教えてください。
-
溶体化処理について教えてください。
-
抗磁力・焼きなましについて教えてください。
-
焼き入れについて教えてください。
-
歪取り焼鈍で硬度は変化しますか。
-
冷却するときの質量とはどのようなものでしょうか。
-
インコネル718の焼鈍について教えてください。
-
ポット炉で投入するガスを途中で変えることは出来ますか?
-
ポット炉と連続炉の違いはありますか?
-
ポット炉と連続炉の使い分けはどのような理由でしょうか?
-
「残留磁束密度」の意味について教えてください。
-
「実効透磁率」の意味について教えてください。
-
「インダクタンス」の意味について教えてください。
-
「保磁力」の意味について教えてください。
-
「コアロス」の意味について教えてください。
-
「渦電流損」の意味について教えてください。
-
「ヒステリシス損」の意味について教えてください。
-
「最大透磁率」の意味について教えてください。
-
「初透磁率」の意味について教えてください。
-
「透磁率」の意味について教えてください。
-
「最大磁束密度」の意味について教えてください。
-
「飽和磁束密度」の意味について教えてください。
-
「ソルバイト」の意味について教えてください。
-
「セメンタイト」の意味について教えてください。
-
「パーライト」の意味について教えてください。
-
「変態点」の意味について教えてください。
-
「残留オーステナイト」の意味について教えてください。
-
「オーステナイト」の意味について教えてください。
-
「フェライト」の意味について教えてください。
-
不活性ガスについて説明してください。
-
還元性ガスについて説明してください。
-
水素雰囲気熱処理を窒素でおこなった場合はどうなりますか?
-
ステンレスの硬度を上げることは可能ですか?
-
銅材料の硬度を下げることは可能ですか?
-
熱処理後に酸洗の必要はありますか?
-
極細な部品でも熱処理可能ですか?
-
薄板の熱処理は可能ですか?
-
コーテイング材の熱処理は可能ですか?
-
メッキを拡散処理したいのですが可能ですか?
-
ステンレスの磁気焼鈍は可能ですか?
-
部品どうしがくっついてしまいます。原因を教えてください。
-
熱処理後に変色しました。原因を教えてください。
-
熱処理後は錆びやすくなりますか?
-
熱処理で変形しますか。
-
光輝焼鈍BAという表記はどのような意味ですか?
-
露点とはどのような意味ですか?
-
アルゴンガスでの熱処理はどのような時に使用しますか?
-
窒素雰囲気の熱処理はどのような時に使用しますか?
-
粉末の熱処理は可能ですか?
-
水素雰囲気熱処理とはどのような熱処理ですか?
-
保磁力A/mという表記はどのような意味ですか?
-
析出硬化とはどのような熱処理ですか?
-
固溶化とはどのような熱処理ですか?
-
磁気焼鈍とはどのような熱処理ですか?
-
応力除去とはどのような熱処理ですか?
-
焼きなましとはどのような熱処理ですか?
熱処理条件
-
洋白(キュプロニッケル)の焼鈍温度はどれくらいでしょうか。
-
ケイ素鋼の磁気焼鈍を行いたい。
-
SUS440Cの磁性を熱処理で消磁することはできますか。
-
応力除去焼鈍の冷却方法について教えてください。
-
雰囲気ガスは加圧状態で使用するのでしょうか。
-
インコネルの析出硬化処理の温度が知りたいです。教えてください。
-
磁気焼鈍対象がメッキ処理してある場合はメッキ剥ぎの前処理が必要でしょうか。
-
黄銅の再結晶温度を教えてください。また黄銅の熱処理温度は何度ですか。
-
窒素ガスの露点を下げるにはどうしたらよいでしょうか。
-
磁気焼鈍と窒素雰囲気の相性について教えてください。
-
磁気焼鈍の処理温度について教えてください。
-
応力除去焼鈍処理の温度について教えてください。
-
錆とりは何度で行えばよいでしょうか。
-
600°Cまで炉冷して600°Cから急冷するのはなぜですか。
-
溶体化処理の昇温速度について教えてください。
-
銅C1100P-1/4Hの熱処理・銅C1100P-1/4Hの熱処理方法について教えてください。
-
純銅の加工硬化の歪み取りの条件を教えてください。
-
酸化スケールについて教えてください。
-
SUS430の磁気焼鈍を行う場合に加熱時間は重要なのでしょうか。
-
SUS430の磁気焼鈍は、800~900°C、徐冷 とありますが、どういうことでしょうか。
-
BeCu材への処理は可能でしょうか。処理温度は350度ほどです。
-
インコネルの析出効果の条件やインコネル718の析出硬化条件について教えてください。
-
析出強化において効率的に高強度化させるためには、どのような時効処理を行えばよいですか。
-
78%パーマロイの最適熱処理条件パーマロイ薄い箔(0.02×30×100mm)1枚の熱処理をお願いした場合のお見積額を教えてください。
-
アルゴンを使用した熱処理に対応していますか。
-
SKD11完全焼きなましに対応していますか。
-
熱処理時に使用するガスはどのぐらいありますか。
-
焼鈍時にゆっくり冷やさず急冷した場合どうなりますか?
-
焼きなまし処理の温度について教えてください。
-
ステンレスの残留応力をなくすにはどうしたらよいか、教えてください。
-
快削黄銅の熱処理について教えてください。
-
SUS630を荒加工後に固溶化熱処理と析出効果処理を施しH1025にすることができるのでしょうか。
-
磁性焼鈍の冷却毒度について教えてください。
-
SUS316Lの低温焼きなましの温度範囲は何度でしょうか?
-
材質はSUS304でサイズは400mm×400mm×400㎜以内で、板金加工後にファイバーレーザー溶接した構造物、数量1台を熱処理した場合の金額と納期を知りたいです。
-
炭素を水素雰囲気下で1000℃で熱処理したらどうなるか教えてください。
-
ハステロイの焼鈍について教えてください。
-
無酸素銅の応力除去焼鈍について教えてください。
-
S10Cで磁気焼鈍で磁気が抜けないので850℃→900℃(再焼鈍)まで 上げたところ2.2%しか下がらないので950 or 1000℃まで上げても大丈夫でしょうか?
-
SUS430の抗磁力を下げる磁気焼鈍は何度ぐらいで処理するのが適切ですか?
-
焼鈍時間について教えてください。
-
還元温度について教えてください。
-
ファンで風を当てて冷却しても徐冷と言えますか。
-
インコネル718の熱処理条件について教えてください。
-
昇温温度について教えてください。
-
材質「C1220P O材 0.4×365×1200」ない場合は「1/4H材をナマシをしてO材」加工サイズ 30×55×0.4t、数量 1000枚(材料4枚分)の処理は可能でしょうか。
-
SUS630の析出硬化処理の温度条件について教えてください。
-
無酸素銅の焼きなまし条件について教えてください。
-
SUS310Sを固溶化熱処理後、耐力:550以上、引張強さ:510以上、伸び:30以上,硬さ:220HBW以下を確保することは可能でしょうか。
-
銅合金での真空熱処理(アルゴン雰囲気)500℃を希望しておりますが、対応して頂く事は可能でしょうか。
-
銅の焼きなましは通常何時間熱処理しますか。
-
熱処理後に溶接する場合、どの雰囲気で実施するのが理想的ですか。
-
銅めっきを純銅にするために熱処理するには何度での熱処理が望ましいですか。
-
磁気焼鈍のヒートパターンはどのように決めるものですか?
-
水冷しているパイプに材料を流しているが、水冷の適正温度がよくわからないです。教えていただけますでしょうか。
熱処理トラブル
-
SUS304板材φ300x9Tの切削加工をしているのですが、材料ロットごとに加工後の歪が大きく出るものと出にくい物とバラつきがあり困っています。加工歪が出にくくなる熱処理というものもあるのでしょうか?
-
銅板t10×260×260を加工したら0.8中心がへこんでいる時、どんな熱処理をしたらよいでしょうか。
-
熱処理の汚れについて教えてください。
-
純鉄の錆び易さは、焼鈍しても変わりませんか。
-
SUS304に応力除去焼なまし(HAR)処理をしたブロック状の部品を 酸洗いしたところ表面がザラザラに荒れてしまいました(ひどいところは凹凸状に模様)。 熱処理の影響でそういったことが起こることはありますか?
-
脱炭の対策について教えてください。
-
ハステロイはどんな環境で変色・腐食されますか。
-
C1100を光輝焼鈍しています。280℃で処理していますが、赤茶色に変色してしまいます。炉を出る時は問題がありませんが、しばらく置いて置くと、徐々に変色するのですが、原因を教えてください。
-
SUS304を焼鈍したら緑になりました。原因はわかりますか。
-
SUS430の変色について教えてください。
-
SUS630の析出硬化処理で硬度が出ない原因について教えてください。
-
ステンレスは何で700℃で緑になるのか教えてください。
-
ステンレスの熱処理で、ステンレスは腐食しているのですか。
-
c2700材を焼鈍したら変色しました。原因を教えてください。
-
水素脆化が起きるとクラックが発生しますでしょうか。BeCuに対して窒素雰囲気で処理してもらったことがあるのですが、赤っぽくなってしまいました。
-
熱処理によって透磁率は低下することはありますか。
-
溶着を防ぐ方法について教えてください。
-
熱を加えると劣化しやすくなるのでしょうか。
-
SPCCに浸炭焼き入れを行った後に磁気焼鈍を行う事での懸念点はありますでしょうか
-
熱処理で微細加工部が溶ける事はありますか? ※刻印用の文字(1㎜程度の数字アルファベット)
-
磁気焼鈍処理時の寸法変化を最小限にする方法はありますでしょうか?
-
熱処理した鋼材錆が出ました。錆除去のため、酸洗いしていいですか。また鋼材の硬度に影響がありますか。
-
ステンレス材の固溶か処理で表面は酸化して黒くならないのですか?
-
磁気焼鈍は、保持力が高すぎた場合、再処理で修正できますか?
-
鉄箔(SUY)を窒素雰囲気で熱処理した場合、鉄と窒素は反応してしまうのでしょうか
-
オーステナイトは急冷すると磁石に着いてしまうでしょうか。
-
時効後の窒化前に常温状態で放置したら酸化が悪影響を及ぼしますか?
-
真空蒸着法でアルミニウム膜を成膜したら黒っぽくなりました。酸化が原因ですか。
-
酸化を防止する方法について教えてください。
-
材料溶着はどのように対策したら良いでしょうか。
-
ステンレスの熱処理について、「ステンレスの場合、微量の油分で変色します。」と記載がありますがあ、なぜ油があると変色するのか、理由を教えていただけないでしょうか。
-
脱炭現象を防ぐについて教えてください。
-
オーステナイト系の熱処理は収縮や膨張しますか?
-
油の焼き付きについて教えてください。
-
99.9%水素でステンレス鋼帯の焼鈍を行っています。理想露点値―40℃で―30℃の時に鋼帯着色を起こします。-30℃の時に着色を起こした際に、 TV値(スピード)を下げたら着色が少なくなりましたがなぜ、着色が少なくなったのでしょうか?? ※鋼種SUS304、SUS301
-
SUJ2(鉄)に光輝熱処理を実施した場合、錆は発生しますか。また時間がたつと錆びてくるということはありますか?
-
熱処理した後、硬度にバラつきが出るのは何故ですか。
-
SUS304のブロック材(50x100Xt20)mmに表面処理時に400℃に加熱するのですが、歪んだりしますでしょうか。平面度が重要なので教えてください。
-
ステンレス鋼の熱処理時に水素ガスを使いながら熱処理を行うのですが、表面が酸化してしまいます。酸化を防止するためにどんな方法があるか教えてください。
-
水冷温度が低すぎる事や一定で無いことが理由で色調、軟化度に変化はみられますか?
研究・開発
-
コバールの酸化被膜温度はわかりますか?
取引条件・流れ
-
時効硬化処理の納期はどれくらいですか?
-
焼鈍処理の納期はどれくらいですか?
-
磁気焼鈍処理の納期はどれくらいですか?
検査
-
硬度の管理は可能ですか?
-
露点管理は行っていますか。
-
熱処理の品質保証はどのようにされていますか。
-
試料本体の温度を測定することは可能ですか?
-
保磁力の測定は可能ですか。
その他
-
納期について教えてください。
-
どのような熱処理ができますか。
-
水素炉を設置する場合、消防への届出は必要になりますか。
-
磁気焼鈍の納期はどのくらいでしょうか。
-
カーボンノヒーターは使用していますか?
-
連続炉はありますか?
-
熱処理にどのようなガスを使用することができますか?
-
長時間の熱処理は可能ですか?